
家庭菜園を始めるとき、最初に悩むのが「どのミニトマト苗を選ぶか」という点ではないでしょうか?私も初めてミニトマトを育てたときは、どの品種が一番収穫できるのか、どれが育てやすいのか全く分からず、試行錯誤を繰り返しました。
その結果、失敗と成功を重ねた経験を元に、今回は「おすすめのミニトマト苗」を紹介します。元ホームセンター店長として、数々の苗を見てきた私が実際に育てて比較した品種をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
多くの人が「どの品種が一番収穫できるのか?」と悩んでいますが、実際に育ててみないとわからないこともたくさんあります。私が育てた結果、成長の速さや収穫量、味において優れた品種がいくつか見つかりました。この記事を読んで、あなたも失敗せずに効率よく、そして美味しいミニトマトを育てることができるはずです。
また、苗選びだけでなく、育てる上での注意点やポイントについても詳しく解説していきます。「このままだと損するかも…」と思わないよう、育てやすくて収穫量の多い品種を選ぶことが大切です。無駄に失敗する前に、ぜひこの記事をチェックしてください。
3種類の品種を比較しながら育てました

家庭菜園を始める際、どの品種を選ぶかが成功の鍵を握っています。
私は実際に、3種類のミニトマト苗「アイコ」「あまぶる」「純あま」を育てて、その違いを比較してみました。その結果、収穫量が最も多かった品種は「純あま」でした。
向かって左から
- アイコ(208円)
- あまぷる(328円)
- 純あま(328円)
で検証しました。
アイコとは

「アイコ」「あまぶる」「純あま」の3品種は、いずれも甘みの強いミニトマトとして人気がありますが、それぞれに育て方や収穫量に違いがありました。
まず、「アイコ」は小ぶりの実が特徴で、味はとても濃厚でしたが、収穫量は他の品種に比べて少なめでした。また、育てるのが比較的簡単で初心者にもおすすめできる品種ではありますが、収穫時期にはバラつきがあり、まとまった収穫が得にくいという印象を受けました。
2004年(平成16年)に発表された品種で種でも苗でも、おなじみの品種です。
サカタのタネのミニトマトは女の子の名前が多い事で知られています。
1番安くて、育てる人も多い定番品種です。とりあえず家庭菜園を始めたい人におすすめです。病気に強くて果実割れも少ないです。
| 詳細 | |
| 価格 | 208円 |
| 株間 | 50cm |
| 植付け | 花が咲いたら。アイコの花は同じ方向に咲くので通路に花を向ける |
| 水やり | 水持ちの良い畑には必要ない |
あまぷるとは

次に「あまぶる」ですが、こちらは甘みが強く、食味が非常に良いミニトマトです。しかし、栽培に少し手間がかかるため、定期的な手入れや水やりが欠かせませんでした。成長速度はやや遅く、結果的に収穫量は「純あま」と比較すると少なかったです。
超薄皮で人気の品種です。サクランボのように甘いです。
| 詳細 | |
| 価格 | 328円 |
| 株間 | 50cm |
| 植付け | 4月中旬頃 |
| 水やり | 朝にたっぷりあげる(1日1回) |
純あまとは
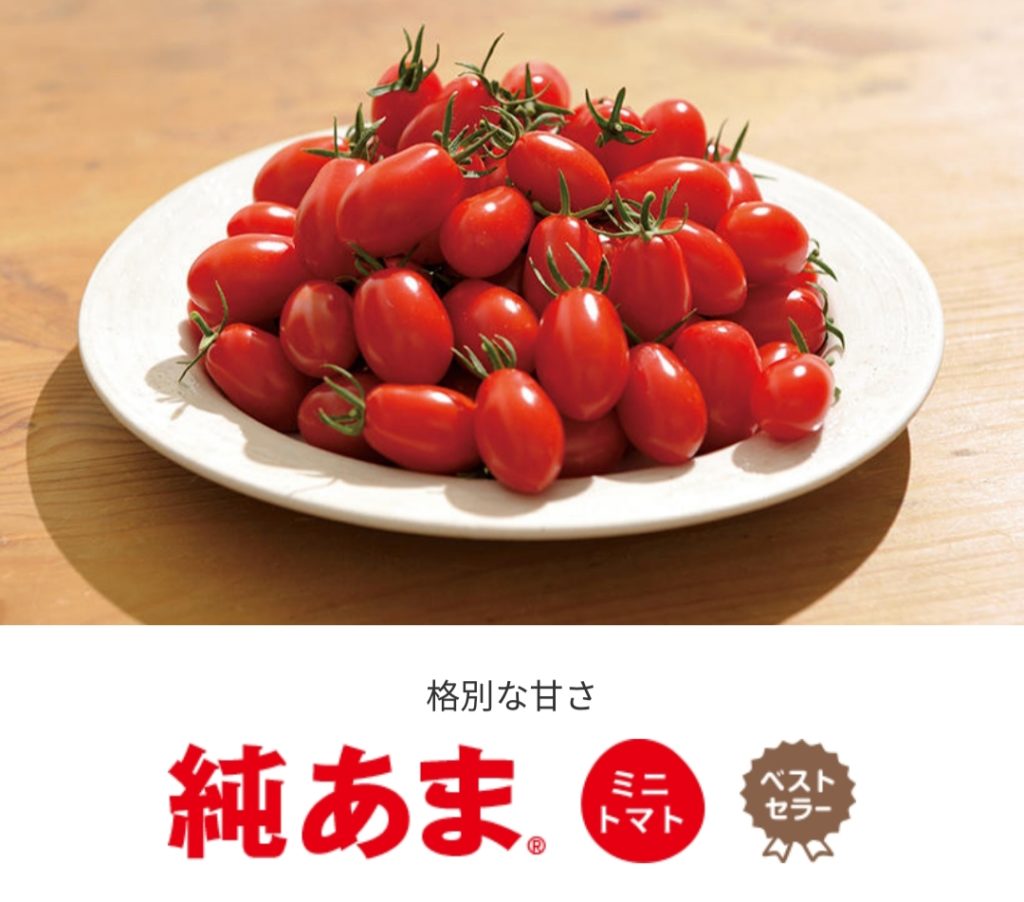
そして、「純あま」は、成長が非常に早く、栄養の吸収も良好なため、しっかりとした収穫が得られました。枝が丈夫で病気にも強く、収穫までの期間が安定しており、他の2品種に比べて非常に多くの実をつけました。
この品種は、少ない手間で確実に収穫量を得ることができるため、特に忙しい方や初心者に最適です。
「純あま」が最も収穫量が多かった理由は、その丈夫さと成長の速さに加え、比較的育てやすかった点が大きいと感じました。もちろん、味や見た目の好みによって品種選びは変わりますが、安定した収穫量を得たいのであれば「純あま」は非常におすすめの品種です。
サントリー本気野菜シリーズの王者です。
まるでぶどうのようにプルプルした食感と甘さが特徴の品種です。デザート感覚で食べられますよ。
| 詳細 | |
| 価格 | 328円 |
| 株間 | 50cm |
| 植付け | 4月中旬 |
| 水やり | 乾燥気味に育てる(やらないか1日1回) |
| 肥料 | 控えめに与える |
4/22(1日目)
庭に植付けました

これからが楽しみです。さっそくわき芽かきをやりました。
ミニトマトを育てる上で重要な作業の一つが「わき芽かき」です。わき芽とは、主幹と葉の間に生えてくる小さな芽のことを指します。この芽を放っておくと、植物が無駄にエネルギーを使ってしまい、結果的に実が十分に成長しないことがあります。
そのため、わき芽かきは収穫量を増やすための重要な作業となります。
また、わき芽かきをすることで、風通しが良くなり、病気の予防にもつながります。湿気が溜まりにくくなるため、葉っぱが蒸れにくく、カビや病害虫のリスクが減少します。特に梅雨時期には、この作業がとても重要です。
さらに、わき芽かきをすることで、株の形を整えやすくなり、管理がしやすくなります。茎がすっきりと立ち上がり、収穫時にも実を見つけやすくなるため、収穫が楽になります。わき芽をすべて取るのではなく、数本残しておくと、補助的な役割を果たしながらも、全体的に整った形を保つことができます。
わき芽かきとは
トマトには非常に多くのわき芽が出てくるので、すぐに取り除くようにしましょう。
サントリーフラワーズのサイトに詳しく動画で紹介されていました。
5/13(21日目)
支柱を立てました

ミニトマトを育てる際に欠かせない作業の一つが「支柱を立てること」です。支柱はトマトの茎を支え、安定した成長を促すために必要不可欠です。特に成長が進んできたミニトマトの茎は、果実の重さで倒れやすくなるため、早めに支柱を立てておくことが大切です。
今回、私もミニトマトが成長してきた段階で、支柱をしっかりと立てることにしました。支柱を立てるタイミングとしては、植物がまだ小さなうちから行うことが理想です。茎が太くなってから支柱を立てようとすると、根や茎を傷つけてしまう可能性があるため、早い段階での準備が大切です。
支柱の選び方ですが、私が使用したのは竹製の支柱です。竹は丈夫で軽量、かつ通気性が良いため、ミニトマトにとっても最適です。また長さも1.5メートルほどのものを選び、トマトが成長するスペースを確保しました。
支柱を立てる作業自体は、比較的簡単でした。支柱を地面にしっかりと挿し、ミニトマトの茎を支柱に固定するために、麻ひもで軽く縛ります。ひもがきつすぎると茎を傷つけてしまうので、緩やかに固定することがポイントです。茎が成長するたびにひもを少しずつ調整して、支柱と茎が密接に接触しないようにしました。
支柱を立てることで、ミニトマトは風に揺れにくくなり、実も安定して育ちます。茎が倒れずにしっかりと立っていることで、光合成がより効率的に行われ、果実が美味しく成長するための環境が整います。また、風通しが良くなるため、病気の予防にもつながります。
支柱を立てたことで、トマトの成長もぐんぐん進み、今後の収穫がますます楽しみになりました。支柱の設置は、しっかりとした土台作りの一歩として、非常に大切な作業だと実感しています。本当は植え付けと同時にやりたかったのですが、やっと出来ました。
6/2(41日目)
あまぷるに芯止まりが起きた

ミニトマトを育てていると、時々「芯止まり」という現象が発生することがあります。今回は、私が育てていた「純あま」の隣に植えていた「あまぷる」に、まさにその芯止まりが起きてしまいました。
芯止まりとは、植物の成長点(トップ)が突然成長を止めてしまう現象で、茎の先端が枯れたり、育ちが止まってしまうことを指します。
この現象が起きる原因として、いくつかの要素が考えられます。
まずは「栄養不足」が大きな原因です。特に、トマトなどの植物は果実が多くなると、株全体が大量の栄養を必要とします。そのため、栄養が不足してしまうと、成長点が弱くなり、芯止まりが起きやすくなります。
私の「アマプル」も、果実が少しずつ大きくなり始めていた時期に芯止まりが発生しました。土壌の栄養が足りていなかったのか、もしくは水分管理が適切ではなかったのか、いずれも原因として考えられます。水分が過剰になりすぎて根が酸欠状態になった場合や、逆に水分が足りない場合も、同様の問題が起こることがあります。
芯止まりが起きたときにまず行ったのは、株の状態をよく観察することでした。枝や葉の色が変わっていないか、根の状態がどうなっているかを確認し、栄養不足が原因である可能性が高いと感じたので、速やかに追肥を行いました。肥料は、ミニトマト専用の液体肥料を使用し、土壌にしっかりと浸透させました。
また、水やりのタイミングを見直し、土が乾燥しすぎないように気をつけました。水分と栄養のバランスを取ることが重要で、特に成長期のミニトマトには定期的なケアが必要です。その後、数日間様子を見守ると、幸いにも芯が再び成長を始め、正常な成長が回復しました。
芯止まりは一度起こると株全体の成長が遅れるため、早期の対応が必要です。このような事態に遭遇した際は、焦らずに原因を特定し、適切な処置を施すことが重要だと学びました。これからも気をつけながら、しっかりと手入れをしていきたいと思います。
生長点がなくなってしまっているので、ここからは脇芽かきを中止して脇芽を伸ばしていきます。あまぷるは病気に弱いのかもしれません。
他の2種類は順調に育っています。
6/21(60日目)
収穫出来るようになった

収穫数の途中経過(左から)
- アイコ2個
- あまぷる1個
- 純あま2個
ついに、育てていたミニトマトの収穫が始まりました!6月21日、栽培開始からちょうど60日目となり、やっと実が色づき始めました。初めての収穫は、何とも言えない喜びがありますね。最初は少し心配でしたが、順調に成長を遂げてくれて本当に嬉しい瞬間です。
特に「純あま」の品種が早い段階で色づき、最初に収穫できました。皮が薄くて甘みが強く、果肉もジューシーでとても美味しかったです。他の品種(「あまぷる」や「アイコ」)も少しずつ色づき始めており、今後の収穫が楽しみで仕方ありません。
最初は「いつ収穫できるだろう?」とワクワクしながら見守っていましたが、実際に収穫できるタイミングになると、その甘さやみずみずしさに感動しました。トマトを育てることの醍醐味を感じた瞬間でした。
収穫する際は、トマトの色がしっかりと赤くなってからが目安ですが、緑の部分がなくなるまで完全に色づく前に収穫しても問題ありません。これからは毎日少しずつ収穫できるようになる予定なので、毎日の成長を楽しみにしています。
これまで育てた過程を思い返すと、苗の選定や支柱の設置、わき芽かきなど、細かい手入れがしっかりと実を結んだことを実感しています。これから暑い夏に向けて、収穫がどんどん増えていくことを楽しみにしながら、引き続き気をつけて育てていきたいと思います。
収穫できるようになったことで、さらに家庭菜園が楽しくなり、毎日が待ち遠しいです。次の収穫もどんな味がするのか、今から楽しみで仕方ありません!
7/25(94日目)
「あまぷる」の元気が無くなった

気温も高くなり、ついにミニトマトの収穫が終わりを迎えようとしています。
栽培開始から94日目、これまで順調に育っていたミニトマトですが、最近は元気がなくなり、成長が鈍化してきました。葉の色がやや黄色くなり、実の数も減少し、最後の収穫が近いことを感じさせる兆しが現れました。
これまでの収穫はとても豊富で、甘くてジューシーなトマトをたくさん楽しませてくれましたが、どうやらが尽きてきたようです。トマトの成長がピークを過ぎると、次第に花芽や実の付き方が減り、葉の色が薄くなる現象が見られます。これは植物が栄養を使い果たして、成長を終わりに向かっているサインです。
もちろん、最後まで少しの実を収穫することはできましたが、これ以上の成長は期待できなさそうです。それでも、今まで育ててきた中で得た収穫はとても満足のいくものでミニトマトの甘さに驚きました。特にサラダや料理に使った時のあの味は、本当に自家栽培ならではの美味しさでした。
ミニトマトの収穫が終わりを迎えることは少し寂しいですが、このトマトを育てた経験を次に生かし、来年にはもっと美味しいトマトを作れるように頑張りたいと思います。最後の収穫をしっかりと味わいながら、この夏の思い出を楽しみたいと思います。
8/15(115日目)
収穫終了

- アイコ31個
- あまぷる10個
- 純あま42個
ついに今年のミニトマトの収穫が全て終了しました。栽培開始から約4ヶ月、8月15日を迎えた時点で、すべての品種が収穫を終えました。振り返ってみると、最も多く収穫できた品種は「純あま」でした!初めての家庭菜園で、たくさんの実を育てることができたことに大きな達成感を感じています。
「純あま」は、育てやすさや収穫量の面で圧倒的な強さを見せてくれました。最初から安定して成長し、実がしっかりとついて、収穫時期も長く続きました。途中で芯止まりや病気の心配もありましたが、しっかりと対策を講じたことで、最後まで元気に育ち続けてくれました。結果的に、最も多くの実を収穫することができ、その甘さと美味しさには毎回驚かされました。
「アマプル」や「アイコ」もそれぞれ素晴らしい実をつけてくれましたが、やはり「純あま」が群を抜いていました。実の大きさ、甘さ、そして安定した収穫量、どれをとっても満足できる結果でした。特に「純あま」は収穫が早く、実が大きくなるのが早かったため、初めての収穫時期に他の品種を凌駕していました。
収穫したトマトを使って、サラダや料理に加えた際には、家族からも「こんなに美味しいトマトができるなんて!」と喜ばれました。
今後は、今年の経験を活かし、さらに成長できるように育て方を改良していきたいと思います。来年も「純あま」を中心に、もっとたくさんの実を収穫できるように、準備をしていこうと考えています。
収穫が終了して少し寂しい気もしますが、今年の経験を胸に、来シーズンに向けて新たな挑戦を楽しみにしています。2ヶ月程の間、収穫を楽しむことができました。
広さが物足りない方は畑をレンタルするという手もあります。
合わせて読みたい
-

-
【手ぶらでOK】畑のレンタルサービスを3社で比較しました!おすすめはここです!
続きを見る
