「V2H」とは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の大容量バッテリーを家庭用の電源として活用できる仕組みのことです。
本記事では、V2Hの導入費用について徹底解説します。機器本体の価格や設置工事にかかる費用の目安に加え、リース利用の費用相場、補助金の活用方法、そして導入の流れまで詳しくご紹介します。
V2Hとは「電気自動車のバッテリーを家庭で使えるようにするシステム」
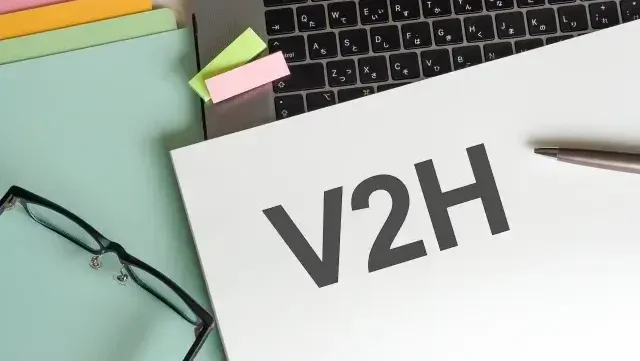
V2Hとは、「Vehicle to Home」の略で、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)のバッテリーに蓄えた電力を家庭に供給する仕組みを指します。
通常、EVは充電した電気を走行に利用しますが、V2Hを導入することでその電気を家庭用電源として活用できるようになります。
この技術により、家庭のエネルギーマネジメントは大きく広がります。停電時の非常用電源としての利用や電気料金の節約、さらには再生可能エネルギーの有効活用まで実現可能です。
特に、災害時のライフライン確保や電力価格の高騰対策として、V2Hは今注目を集めている技術のひとつです。
V2Hのタイプについて
V2Hシステムには、大きく分けて 「単機能型」 と 「ハイブリッド型」 の2種類があります。
それぞれの特徴を理解し、自分のライフスタイルや住宅環境に合ったものを選ぶことが大切です。
単機能型
単機能型は、EV(電気自動車)と家庭の間で「充放電」のみを行うシンプルなタイプです。
EVから家庭へ電気を供給したり、家庭からEVに電気を充電したりと、V2H本来の機能に特化しています。
太陽光発電システムや家庭用蓄電池とは独立しているため、構成がシンプルで設置や運用が比較的容易です。
その分、初期導入コストを抑えやすいというメリットがあります。
ハイブリッド型
ハイブリッド型は、EVとの電気のやり取りに加えて、太陽光発電システムと連携できるタイプです。
発電した電気を効率よくEVに充電し、家庭に再利用できるため、電力変換ロスを抑えながらエネルギー効率を高められます。
また、発電・充電・放電の制御を一体的に行えるため、省エネ効果が高く、住宅全体のエネルギーマネジメントをよりスマートに実現できます。
👉 必要最低限の機能でコストを抑えたいなら「単機能型」、太陽光発電や家庭用蓄電池と組み合わせて効率化を目指したいなら「ハイブリッド型」が適しています。
V2Hはどこで購入できる?

V2Hシステムを購入できる場所は、大きく分けて次の2つです。
1. カーディーラー
電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)を販売しているメーカー系ディーラーでは、車とセットでV2Hシステムを扱っている場合があります。
- メリット
車と同時に導入できるため、わざわざ別で探す必要がない - デメリット
メーカー希望小売価格での販売となるため、専門店より高額になることが多い。また、メーカーや機種の選択肢が限られるケースもあります。
2. V2H専門店
エコ発電本舗などのV2Hを専門に取り扱う店舗では、複数メーカーの製品を比較でき、自宅の環境に合ったものを選べます。
- メリット
カーディーラーより初期費用を抑えられることが多い。補助金制度や製品知識に詳しいスタッフが多く、相談しやすい。 - デメリット
専門店の数が少なく、販売価格の比較がしづらい。
特に、すでにV2H対応の車を所有していて後付けしたい場合は専門店での購入がおすすめです。
V2Hは高電圧を扱う専門的な電気設備であるため、一般の方が自分で購入して取り付けることはできません。
設置には電気工事士の資格が必要となるため、必ず認定された施工業者や販売店を通じて工事を依頼する必要があります。
V2Hの購入金額はどのくらい?

V2Hシステムの導入費用は、メーカーや性能によって差がありますが、工事費込みでおおよそ88万円(税込)〜180万円(税込)が相場です。
これはV2H機器の価格はグレードによって異なり、希望小売価格ベースで100万〜140万円程度となります(実際の販売価格はこれと異なる場合があります)。
さらに、設置工事費用として30万〜40万円程度かかるケースが一般的だからです。
ただし工事費用は、家や駐車場の構造、配線の長さ、選ぶ機種、さらには太陽光発電の有無によっても大きく変動します。
カーディーラーで購入する場合
- 車両(EV・PHV)の購入とあわせてローンに組み込める
- 車の購入と同時に導入できるのがメリット
- ただし、メーカー希望価格での販売が多く、費用は高めになりがち
専門店で購入する場合
- 支払い方法は「一括」「ローン」「クレジットカード」から選べる
- 初期費用を抑えやすい
- ただし、ローンやクレジット払いを選ぶと金利負担が発生するため、結果的に総額は高くなる可能性があります
カーディーラーは「手軽さと安心感」、専門店は「費用の柔軟性」が特徴ですが、支払い方法によっては最終的な金額が変わる点に注意が必要です。
V2Hを購入する際の選び方

V2Hシステムを正しく選べば、電気代の節約や停電対策に大きな効果を発揮します。
逆に、選び方を間違えると「思ったほどメリットを感じられない…」という結果になってしまうことも。
ここでは、V2Hシステムを購入する際に押さえておきたい4つのポイントのうち、まずは「メーカーの違い」について解説します。
主要メーカー3社の特徴
2025年10月現在、V2Hシステムの主要なメーカーは次の3社です。
ニチコン(nichicon)
| モデル名 | 希望小売価格(税込) | 保証年数 |
| VCG-666CN7 (プレミアムモデル) |
987,800円 | 5年 |
2012年に世界で初めてV2Hシステムを発売。
これまでに累計1万台以上を販売しており、国内シェアNo.1。実績と信頼性の高さから、最も多く選ばれているメーカーです。
デンソー(DENSO)
| モデル名 | 価格(税込) | 保証年数 |
| DNEVC-D6075 | 1,671,840円 | 5年 |
世界的な自動車部品メーカー。ただし、V2Hに関してはニチコンのOEM製品を採用しており、自社独自モデルではありません。
デンソーのV2Hシステムは、ニチコンのプレミアムモデルを採用しています。しかし、販売価格はニチコン製品よりも高めに設定されています。
東光高岳(とうこうたかおか)
| モデル名 | 価格(税込) | 保証年数 |
| Smaneko V2H | 825,000円 | 3年 |
東京都江東区に本社を置く電子機器メーカー。
EV・PHV用の急速充電器では日本トップシェアを誇ります。V2H製品としては「Smaneko V2H」を展開しています。
東光高岳のV2Hシステムは価格が比較的安い反面、停電時にEVやPHVへ充電できないという制約があります。
V2H導入に必要な機器と費用相場
1.電気設備(分電盤・切替装置)

V2Hの電力を家庭で利用するには、専用の分電盤や電力切替装置の設置が必要です。
停電時にも家庭の電源を自動または手動で切り替えられるようにするため、配線工事やシステム設定を行います。これらの作業は、安全確保のため有資格の電気工事士による施工が必須です。
前述した通り設置費用は工事費込みでおおよそ88万円(税込)〜180万円(税込)が相場です。
2.V2Hに対応するEVやPHEV

|
メーカー名 |
EV or PHEV |
車種名 |
価格 |
|
スバル |
EV |
ソルテラ |
627万円〜 |
|
トヨタ |
EV |
bZ4X |
550万円〜 |
|
トヨタ |
PHEV |
プリウス |
384万7300円〜 |
|
トヨタ |
PHEV |
アルファード |
1065万円〜 |
|
日産 |
EV |
サクラ |
259万9300円〜 |
|
日産 |
EV |
リーフ |
408万1000円〜 |
|
日産 |
EV |
アリア |
659万100円〜 |
|
ヒョンデ |
EV |
INSTER |
284万9000円〜 |
|
BYD |
EV |
DOLPHIN |
299万2000円〜 |
|
マツダ |
PHEV |
CX-60 |
570万200円〜 |
|
三菱 |
EV |
eKクロスEV |
256万8500円〜 |
|
三菱 |
PHEV |
アウトランダーPHEV |
526万3500円〜 |
|
メルセデス・ベンツ |
EV |
EQA |
775万円〜 |
|
レクサス |
EV |
RZ |
820万円〜 |
|
レクサス |
PHEV |
NX |
749万5000円〜 |
V2Hを導入するためには、当然ながらV2H対応の電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド車(PHEV)が必要です。
ただし、すべての車種がV2Hに対応しているわけではなく、対応可否はV2H機器のメーカーやモデルによって異なります。
EVの価格相場は、軽自動車タイプでおよそ 250万円前後〜、普通車では 300万円程度〜 が目安です。
EV補助金は①国(上限90万円)+②地方自治体(金額は自治体による)
EV購入時に受け取れる補助金について、最も気になるのは「実際にいくら支給されるのか」という点でしょう。ここでは、詳細な条件や申請手続きの前に、まずは2025年度版の補助金額・対象条件・申請期間を分かりやすく一覧にまとめました。
なお、本記事で示す「2025年度」とは、2025年4月1日以降に新車登録(または届出)された車両を対象としていますので、その点をあらかじめご確認ください。
| 項目 | 内容 |
| 補助金名 | CEV補助金(国の補助金) |
| EV(普通車)の上限額 | 最大90万円(基本補助額85万円+加算額5万円) |
| 小型・軽EVの上限額 | 最大58万円(基本補助額55万円+加算額3万円) |
| 交付条件 | ・一定期間内に新車を購入すること ・購入したEV等を一定期間保有(原則4年間) |
| 申請書受付期間 | 初度登録(届出)日から原則1か月以内に申請 |
地方自治体の補助金の有無・上限額・交付条件などは自治体ごとに異なります。
PHEV補助金は①国(上限90万円)+②地方自治体(金額は自治体による)
PHEVを購入する際に見逃せないのが「補助金」です。
中でも多くの方が気になるのは、「実際にいくらもらえるのか」を表にしました。
| 項目 | 内容 |
| 補助金名 | CEV補助金(国の補助金) |
| EV(普通車)の上限額 | 最大60万円(基本補助額55万円+加算額5万円) |
| 交付条件 | ・一定期間内に新車を購入すること ・購入したEV等を一定期間保有(原則4年間) |
| 申請書受付期間 | 初度登録(届出)日から原則1か月以内に申請 |
地方自治体の補助金の有無・上限額・交付条件などは自治体ごとに異なります。
3.太陽光発電システム(オプション)

V2Hは、太陽光発電システムや家庭用蓄電池と組み合わせることで、さらに高い効果を発揮します。
昼間に発電した電気をEVに充電し、夜間に家庭で使用することで、電力会社からの買電を大幅に削減できます。
特にFIT(固定価格買取制度)終了後のご家庭では、「太陽光+V2H」の組み合わせが、余剰電力を無駄なく活用できる最も効率的な選択肢と言えるでしょう。
なお太陽光パネルの設置費用は85.8万円〜143万円が一般的です。
詳細はこちらの記事で解説しました。
合わせて読みたい
-

-
太陽光パネルの費用相場|導入するメリット・デメリットを徹底解説
続きを見る
V2H導入のメリット

充電時間の短縮
一般的な普通充電器(約3kW出力)に比べ、V2Hは約6kWの高出力に対応。
充電時間をおよそ半分に短縮でき、より効率的にEVを活用できます。
電気代の削減
夜間の安い電気料金時間帯にEVへ充電し、日中はその電気を家庭で使うことで、電気代を大幅に節約できます。
(※夜間電力が安くなるプランに加入している場合)
停電時の非常用電源
地震や台風などで停電が発生しても、EVに蓄えた電力を家に供給できれば、照明・冷蔵庫・通信機器・エアコンなどを普段通り使うことが可能です。
バッテリー容量にもよりますが、一般的な家庭であれば1台のEVで数日間生活を維持できるとされています。
環境への貢献
太陽光発電と組み合わせることで、昼間に余った電気をEVに蓄電し、夜間に利用可能。再生可能エネルギーの自家消費率を高め、CO₂排出削減にもつながります。
V2H導入のデメリット

V2Hには普通充電器と比べていくつかの注意点もあります。
導入コストが高い
V2H機器本体の価格に加え、設置工事費用も必要となるため、初期投資は大きくなります。
また、サイズが普通充電器より大きいため、設置にはある程度のスペースが必要になるケースもあります。
こうした点を踏まえた上で、費用対効果や設置環境をよく確認しながら導入を検討することが大切です。
V2Hシステムを導入するなら
テスラ認定の「エコ発電本舗」がおすすめ
エコ発電本舗は、施工品質の高さやサポート体制の充実度で注目を集める人気の太陽光発電サービスです。
テスラ認定の販売施工店としての信頼性に加え、全国対応・豊富な導入実績を誇り、多くのユーザーから高い評価を得ています。
太陽光発電や蓄電池の需要が急速に高まる一方で、施工不良によるトラブルも増加しています。中でも、「太陽光パネル設置後の雨漏り」や「分電盤の発火」、「エコキュート配管からの漏水」といった深刻なケースは、ご自宅に大きな被害を与える恐れがあります。
そんな中、エコ発電本舗は施工品質に徹底してこだわり、
- 太陽光発電に関する雨漏り0件
- エコキュートの水漏れ0件
という、極めて優れた実績を維持しています。
| 制度・仕組み名 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ゼロホーム |
| 提携業者数 | 自社施工 |
| Google口コミ | ★4.2(330件) |
| 対応エリア | 全国 |
| 実績・特徴 | ・月間12万人が利用 ・日本最大級の太陽光・蓄電池サイト ・太陽光発電の雨漏り0件 ・エコキュートの水漏れ0件 ・価格満足度97% ・サポート満足度96% ・友人に勧めたい96% ・テスラの認定販売施工店 |
2025年10月2日時点のデータです。
もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をどうぞ
エコ発電本舗の評判は最悪?口コミから分かる真相とメリット・デメリット
VH2の見積もりサイト6社の比較一覧表

見積もりサイトは複数ありますが、「結局どれが良いの?」と迷ってしまう人は多いはず。
そこでこの章では厳選した6社を徹底比較しました。
※この表は左右にスクロールできます。
| サイト名 | 実績・特徴 | 種類 | 提携社数 | 紹介社数 | 対応エリア | Google口コミ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコ発電本舗 | ・月間12万人が利用 ・日本最大級の太陽光・蓄電池サイト ・太陽光発電の雨漏り0件 ・エコキュートの水漏れ0件 ・価格満足度97% ・サポート満足度96% ・友人に勧めたい96% ・テスラの認定販売施工店 |
自社施工 | 自社施工 | 自社施工 | 全国 | ★4.2(330件) |
| ソーラーパートナーズ | ・依頼件数ランキングで4年連続No.1 ・累計利用者17万人以上 ・審査通過率9.8%(業界最高レベル) ・お断り代行 ・工事完了保証 |
一括見積もり | 約600社 | 最大3社 | 全国 | ★4.3(185件)。 |
| ハチドリソーラー | ・初期費用0円で設置可能 (しかも契約満了後に0円でもらえる) ・累計2万件の施工実績 ・太陽光パネルをリースして使用 |
リース型 | 約100社 | - | 全国 | ★3.8(13件) |
| タイナビ (グッドフェローズ) |
・累計利用者20万人 ・顧客満足度98% ・ローン活用で初期費用無料 ・見積もりまでが早い |
一括見積もり | 約270社 | 最大5社 | 全国 | ★1.8(5件) |
| 節電プロ (BCS JAPAN) |
・初期費用0円で設置可能 ・地域密着型 |
自社施工 | 自社施工 | 自社施工 | 東京都内 | ★2.3(3件) |
| グリエネ | ・上場企業が運営 ・利用者数が累計10万人以上 |
一括見積もり | 約450社 | 最大5社 | 全国 | ★1.0(2件) |
※2025年9月29日時点のデータです。
V2Hはどこで購入するべき?のまとめ

電気自動車やプラグインハイブリッド車の普及に伴い、注目を集めているのが「V2Hシステム」です。
導入すれば、電気代の節約や災害時の停電対策として大きな効果を発揮します。
ただし、購入先や選び方を誤ってしまうと、予想以上に費用がかかったり、本来期待していたメリットを十分に得られないこともあります。
インターネットで調べられる情報には限界があるため、不安や疑問がある場合は、専門知識を持つ販売店やカーディーラーに直接相談するのが安心です。

